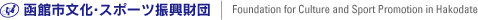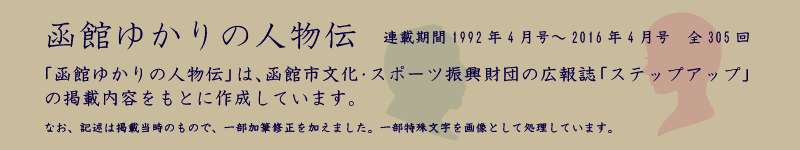石川啄木 (いしかわたくぼく) 1886年~1912年
「死ぬときは函館へ行って死ぬ」と手紙に残すほど函館を愛していた漂泊の詩人・石川啄木。

明治19年2月20日、岩手県南岩手郡(現・盛岡市)日戸村の曹洞宗日照山常光寺住職の一禎と母カツの長男として生まれる。本名一(はじめ)。翌年、父一禎が北岩手郡渋民村宝徳寺に任じられ、一家で渋民村に移転する。
渋民尋常小学校、盛岡高等小学校を経て、明治31年、盛岡尋常中学校に入学。先輩金田一京助のすすめで雑誌「明星」を愛読し、その影響を受ける。34年12月、「白羊会詠草」25首を「翠江」の筆名で「岩手日報」に掲載する。啄木の短歌が活字になった最初の作品となる。
明治35年10月、文学をもって身を立てるべく退学届けを提出し上京する。渋谷の新詩社に与謝野鉄幹・晶子夫妻を訪問。以後、夫婦の知遇を得る。36年12月、「明星」に「啄木」の筆名で発表した「愁調」と題する5編の長詩が載り、新詩社内外の注目を集める。この年、堀合節子との恋愛が進む。37年父一禎、宗費を滞納し、宝徳寺住職罷免の処分を受ける。
明治38年5月、処女詩集『あこがれ』刊行。翌月、啄木は盛岡に帰り堀合節子を妻として迎える。39年4月、渋民尋常高等小学校代用教員となる。小説家をめざして、「雲は天才である」「面影」を書く。
明治40年5月5日、渋民村を出て函館に到着する。函館商業会議所の臨時雇となる。苜蓿社(ぼくしゅくしゃ)の仲間となり同人雑誌「紅苜蓿(べにまごやし)」の編集をする。経済的にも援助を受けることになる宮崎郁雨(本名・大四郎)と知り合う。
6月、弥生尋常小学校代用教員となる。翌月、青柳町18番地に新居を構え、妻子を迎える。8月、函館日日新聞社遊軍記者となり、ようやく函館の生活に馴染むが、8月25日、大火のため学校も新聞社も焼け、再び生活の危機に立つ。9月13日、札幌に向かう。北門新報社に入社するが、わずか2週間にして小樽日報社の創業に参加、記者となる。12月、社の内紛に関して事務長と争い退社。
明治41年1月、釧路新聞社に勤務することになり、単身赴任。芸者小奴を知り交情を深めるが、社の上司に対する不満と東京での創作活動へのあこがれから上京を決意し、4月5日釧路を去り、函館を経て上京する。函館に残された妻節子は宝尋常高等小学校の代用教員となる。
明治42年、雑誌「スバル」創刊に参加。東京朝日新聞社に校正係として入社。家族を迎えるまでの約2ヶ月間の苦悩を「ローマ字日記」に記す(後に日記文学の傑作として文学史に刻まれる)。
明治43年6月、幸徳秋水ら無政府主義者の「大逆事件」報道に衝撃を受け、以後社会主義思想に関心を持つ。12月1日、処女歌集『一握の砂』刊行。一首三行書きの「生活を詠う」その独特の歌風は、歌壇内外から注目され、第一線歌人の地位を確立する。
明治45年4月13日、早朝危篤に陥り、父一禎、妻節子、友人若山牧水に看取られて死去。病名は肺結核。享年27歳。没後、歌集『悲しき玩具』が刊行される。
現在の墓碑は、大正15年、宮崎郁雨等によって立待岬に建てられた。墓石の前面には「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる」(一握の砂)の一首が彫り込まれている。